退職したらやることの順番は?早くやらないとヤバい手続きもあるぞ!

早期退職・セミリタイアして退職後は当然会社が面倒を見てくれることはなくなり、手続きなど全て自分自身での対応が必要になります。
具体的にどんな手続きが必要?
手続きの中には「退職後いつまで」といった期限付きのものもあります。健康保険などは手続きを怠ると無保険状態になってしまうので注意が必要ですね。
この記事では会社を退職後、スムーズにリタイア生活に移行するための必要な各種手続きについて解説していきます。
この記事でわかること
- 退職時に会社から受け取る書類・返却する書類
- 退職後早い段階で行うべき各種手続きについて
この記事を読めば会社を退職後に必要な手続き一通りについて理解できるようになります。
せひ最後まで見ていってください。
最初に結論!セミリタイア・早期退職後に必要な手続きチェックリスト一覧
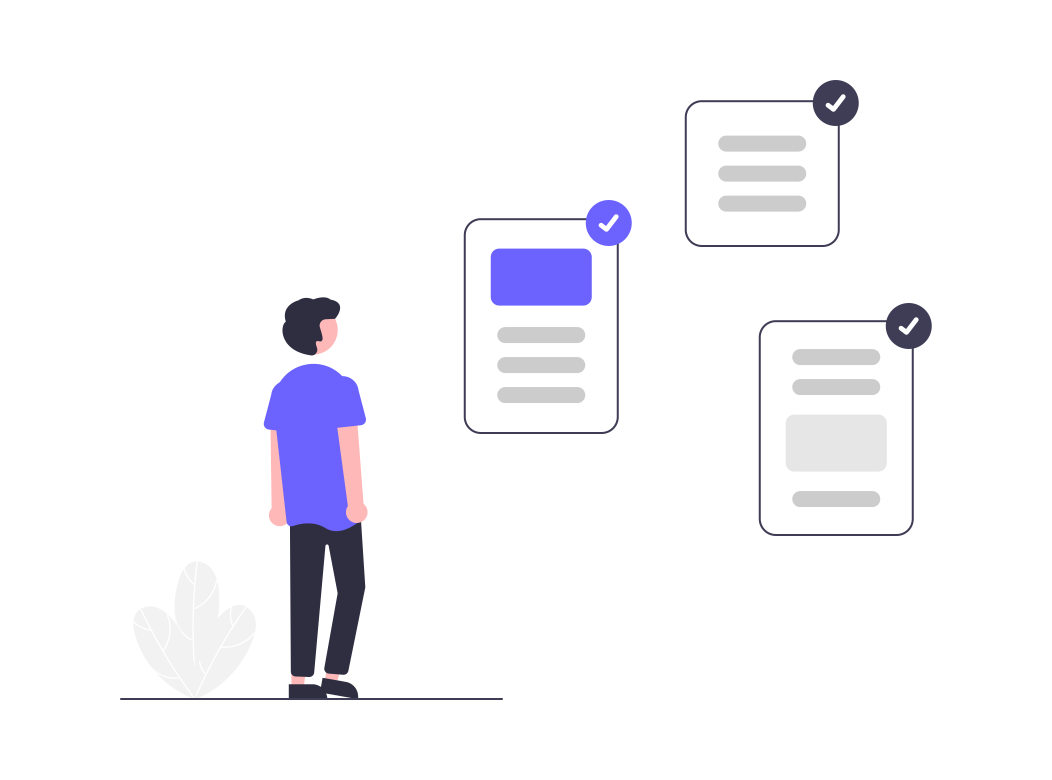
【退職後すぐに必要な手続き】
1. 健康保険の切替(退職日翌日から14~20日以内)
選択肢A:任意継続被保険者制度
- 期限: 退職日翌日から20日以内
- 場所: 住所地を管轄する協会けんぽ支部
- 必要書類: 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書、本人確認書類
- 特徴: 最大2年間継続可能、保険料は全額自己負担(在職中の約2倍)
選択肢B:国民健康保険への加入
- 期限: 退職日翌日から14日以内
- 場所: 自治体の役場
- 必要書類: 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、通帳、印鑑、マイナンバー
- 特徴: 保険料は自治体ごとに異なる
2. 年金の切替(退職日翌日から14日以内)
- 場所: 自治体の役場
- 必要書類: 年金手帳、退職日確認書類(離職票・健康保険資格喪失証明書)、本人確認書類、印鑑
- 内容: 厚生年金から国民年金(第1号被保険者)への切替
- おすすめ: 付加保険料制度(月額400円で将来の年金が増額)の申込み
3. 雇用保険(失業給付)の手続き
- 場所: ハローワーク
- 必要書類: 離職票、マイナンバー確認書類、本人確認書類、写真2枚(縦3cm×横2.5cm)、印鑑、預金通帳またはキャッシュカード
- 条件: 働く意思がある場合のみ
- 受給期間: 原則、退職日翌日から1年間
4. 確定拠出年金の移換手続き
- 対象: 企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者
- 内容: 個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換
- 場所: 運用管理機関(金融機関)
- 注意: 手続きを怠ると自動移換され、非課税メリットが失われる
【翌年に必要な手続き】
5. 所得税の確定申告(翌年2月中旬~3月中旬)
- 場所: 税務署または電子申告(e-Tax)
- 必要書類: 源泉徴収票、控除証明書類など
- 内容: 年度途中退職の場合、払いすぎた税金の還付を受ける
6. 住民税の納付
- 内容: 前年の所得に対する住民税を後払い方式で納付
- 注意: 退職翌年・翌々年も会社員時代の所得に対する住民税の支払いが続く
【必要に応じて行う手続き】
7. 扶養の追加手続き
- 対象: 配偶者や子どもがいる場合
- 内容: 健康保険、国民年金第3号被保険者への切替など
8. 住所変更手続き
- 対象: 退職に伴い引っ越す場合
- 場所: 転出元・転入先の役場
- 関連: 運転免許証、マイナンバー、銀行口座などの住所変更も
9. クレジットカード・ローンの見直し
- 内容: 退職前に必要なカードの申込み、ローン審査を済ませておく
- 注意: 退職後は審査が通りにくくなる
10. 各種保険の見直し
- 対象: 生命保険、医療保険、火災保険など
- 内容: 収入減に合わせた保障内容・保険料の見直し
【事前準備として推奨される手続き】
- 退職前に離職票、健康保険資格喪失証明書、源泉徴収票などの発行を会社に確認
- 各保険料の試算を行い、家計の見通しを立てる
- 必要書類(年金手帳、マイナンバーカード、印鑑、通帳など)の準備
退職時に会社から受け取る書類、返却する書類。貰い忘れるとヤバい!

会社から受け取る書類、返却する書類があります。
基本的には会社から指示があると思いますが、退職後の手続きに必要な重要書類なので過不足がないかの確認が必要です。
会社から受け取る書類
離職票
失業保険の受給手続き、年金の切替手続きに必要です。
雇用保険被保険者証
転職など再就職する際に就職先企業に提出する書類です。セミリタイア後であればできればお世話になりたくない書類です。
健康保険資格喪失証明書
国民健康保険への切替手続きに必要な書類です。
源泉徴収票
こちらも転職など再就職する際に就職先企業への提出に必要です。セミリタイア目的の場合は確定申告の際に必要になります。
会社へ返却する書類
健康保険証
退職する日までは利用可能です。退職後にこの健康保険証を提示して病院を受診しても無保険状態なので医療費は全額負担になります。くれぐれもご注意を。
その他会社から預かっている備品
もっと詳しく!セミリタイア後に必要な手続きの詳細手順を解説

健康保険
会社を退職後、速やかに健康保険の手続きが必要です。
健康保険には2つの選択肢があります。
- 任意継続被保険者制度の利用
- 国民健康保険への切替
両方の保険料を試算して、自分にメリットのある方を選択すると良いと思いますよ。
任意継続被保険者制度の利用
在職していた会社からの健康保険に継続して加入し続けることができます。
条件はふたつです。
- 継続して加入できる期間は最大2年
- 利用条件として退職前に2カ月以上の被保険者期間が必要
継続とはいっても在職中は会社が保険料の一定割合を負担してくれていましたが、退職後は全額自己負担になります。
会社が何割負担をしていたかは就業規則に記載されているはずなので、退職前には確認しておくのがよいと思います。
多くの会社は50:50の折半なので、会社員時代に払っていた保険料の倍くらいの支払い額になると考えておけばだいたいOKです。
退職後に支払う保険料は、退職時点の標準報酬月額にもとづき都道府県ごとの保険料率で決まります。
在職中と違う点は標準報酬月額に30万円の上限が付くことです。
収入の多かった方であれば支払う保険料はさほど変わらないかもしれません。
健康保険料の改定はひんぱんに行われます。最新は都度、自分で確認するようにしてください。
保険料は全国健保保険協会のHPで確認できます。
【ちなみに令和3年時点】
東京都
標準報酬月額が上限30万円
このケースでの保険料は月額34920円です。
国民健康保険への切替
任意継続を使用しない場合は国民健康保険への切替が必要です。
保険料は自治体ごとに異なります。
各自治体の役場HPに保険料率が記載されている場合もありますが、源泉徴収料を持って窓口で相談するのがいちばん正確です。
- ■必要書類
-
健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、通帳、印鑑、マイナンバー
- ■申し込み場所
-
自治体の役場
- ■申し込み期限
-
退職日の翌日から14日以内
年金の切替
会社から退職し誰かの扶養に入らない場合は、厚生年金から国民年金の第1被保険者に加入することが義務付けられています。
自治体の役場で手続きでき、年金保険料は令和3年時点で月額16610円です。
詳細は日本年金機構HPの国民年金に記載されています。
ちなみに国民年金には付加保険料納付の制度があって月額400円を余計に保険料として支払うと、将来の年金受給額が増額されるかなりコスパのイイ制度です。
具体的には200円×付加保険料を収めた期間分の額が年間の年金受給額に付加されます。
【例えば】
50歳でセミリタイアして60歳まで付加保険料を支払ったケースの場合
24000円=(200円×120カ月)
24000円が年金受給額に毎年加算され続けます。
2年で元が取れるので利用しない手はないと思います。
日本年金機構HPの付加保険料納付のご案内に詳しく記載されているので参照してみてください。
かなり、お得な制度ですね。こういうことを知らない人は損してしまいますよね。
-
年金手帳、退職日が確認できる書類(離職票・健康保険資格喪失証明書)、本人確認書類、印鑑
- ■申し込み場所
-
自治体の役場
- ■申し込み期限
-
退職日の翌日から14日以内
雇用保険
会社を退職後(失業後)に働く意思があるなどの条件を満たした場合に失業給付を受けられる制度です。
受給の意思がある場合は手続きが必要です。受給期間は原則、退職日翌日から1年間です。
手続きの詳細はハローワークHPの雇用保険手続きのご案内から確認できますので一読を。
-
離職票、個人番号が確認可能な書類(マイナンバー・通知表)、身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード)、最近の写真2枚(縦3cm×横2.5cm)、印鑑、預金通帳やキャッシュカード
- ■申し込み場所
-
ハローワーク
確定拠出年金
在職している会社が企業型確定拠出年金(企業型DC)を採用していた場合、個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換が必要です。
運用管理機関に問い合わせれば移換手続きができます。
その際にiDeCo口座を新規に開設する必要があるのであわせて手続きします。
移換手続きを怠ると口座内資産が現金化されて国民年金基金連合会の方へ自動移換されます。
こうなると非課税メリットを受けられないばかりか、毎年手数料を徴収されるので相当なデメリットです。
在籍していた会社に企業型DCの制度がなく、もともとiDeCoで運用されている方はそのままでOKです。
税金
所得税
会社員の所得税はその1年間の収入の見込みから年間の税額が徴収される前払い方式なので、年度途中で退職した場合納税額は多めに支払うことになるはずです。
翌年の2月中旬〜3月中旬の期間で確定申告することで還付を受けられるので忘れずに申告が必要です。
会社員時代から副業や株式の控除で確定申告に慣れておくとイイですよ。
住民税
住民税は所得税と違い1月〜12月の所得に対しての課税額を翌年の6月〜翌々年5月に支払う後払い方式です。
退職月が1月〜5月と、6月〜12月で支払いの方法が異なってきます。
1月〜5月
同年5月分までの納税額を退職時に一括で支払います。
同年6月以降支払い分は役場から納税通知書が送られてきます。
6月〜12月
翌年の5月分までの支払い額を一括もしくは分割支払いかを選択します。
一括の場合は会社の給与額から天引きしてくれると思います。
翌年6月〜翌々年5月分は役場から納税通知書が送られてくるはずなのでそちらを使って納税します。
ちなみに住民税はその年の所得に対する税金を翌年〜翌々年に払う後払い方式と説明しました。
セミリタイアで会社を退職した翌々年まで会社員時点の所得に対する税率分の支払いが続きます。
収入が0なのに住民税はしっかりとられるので注意が必要です。
会社員時代に高給取りだった人が退職翌年の住民税で困窮する話は聞きますものね。
最後に。セミリタイア達成後も気を抜かずに!

いががでしたか?
セミリタイアを達成し、会社を退職した後に必要な主な手続きについて解説してきました。
- 退職時に会社から受け取る書類・返却する書類
- 退職後早い段階で行うべき各種手続きについて
これまではどれも会社が手続きを代行してくれていたり、折半で保険料を負担してくれていたりと、いたれりつくせり状態であったことがよくわかります。
退職後はこういった処理を全て自分自身でやっていく必要があります。
しっかりと学んで抜け漏れのないようにしていきたいものです。
この記事があなたの役に立つようであればうれしく思います。






