楽天証券とSBI証券どっちを使うべきか?⇒結論:両方使え!

こんな疑問を解決します。
証券会社は各社特徴があって選ぶのがむずかしいですよね?
中でも二大ネット証券の楽天証券とSBI証券、どちらにすべきかで悩む人が多いと思います。
結論からいってしまえば、両方を使い分けるのがおすすめです。
楽天証券、SBI証券それぞれのメリットを活かすことで、効率的に資産形成ができるからなんです。
わが家は両方を使っています。
一社だけだと「これが惜しいなー」というところも、二社なら弱点を補完できるので資産形成のスピードが変わることを実感していますね。
この記事では楽天証券、SBI証券の二社を使いこなすために主に三つのポイントで解説をします。
この記事でわかること
この記事を読めば楽天証券、SBI証券をどう使い分ければいいのかがわかります。
資産形成には証券口座の上手な使い方が必須です。「知らないだけで損をしてしまう」なんてことにならないよう、ぜひ最後まで見ていってください。
楽天証券とSBI証券を使い分けるメリットは?

複数の証券会社で資産運用することにはメリットがあります。
メリット①:各社いいとこどりで効率よく資産形成ができる
証券各社にはそれぞれ売りにしている強み部分があります。
強み部分は上手に利用すれば効率よく資産形成を進められるので、利用者側はなるべく取り込みたいんですよね。
例えば・・・本記事のメインテーマである楽天証券とSBI証券を例にすると、以下がそれぞれの強み部分にあたるわけです。
楽天証券:楽天経済圏の他サービスとの連携によるポイントのためやすさ
SBI証券:取扱銘柄数の数や取引手数料の安さ
利用者側としては楽天証券でポイントをためつつ、SBI証券では安い手数料で投資したい!と考えますよね。
使い分けのメリットは、各社の強み部分をいいとこどりして、効率よく資産形成をすることにあります。
ただし、数が増えすぎると管理が大変になってしまうので、最大でも二社がいいところだと思います。
ちなみに証券口座を複数持っていても、口座維持手数料などはかからなのでコスト面でのデメリットはありません。
メリット②:IPOの当選確率が上がる
IPOは上級者向けの投資方法です。
初心者の方はスルーしていただいて大丈夫です。
新規公開株(IPO)を購入するには、【購入する権利】を抽選で手に入れなければなりません。
抽選なので抽選券が多いほど当選確率が上がりますよね。
複数の証券口座を持つことは抽選券を複数持つことと同じです。
IPOは公開直後の初値が高くなる傾向があるので、公開価格で購入し初値で売ることで、高確率で利益をとれることから人気の商品なんです。
楽天証券を使うメリット。楽天ポイントが熱い!

楽天証券のメリット、強み部分について解説します。
投資信託の積立に楽天カード決済を利用できる
楽天証券は投資信託の積立に、楽天カードのクレジット決済を利用できます。
ポイント還元率は100円で1ポイント(1%)、上限は1カ月5万円です。
クレジット決済が利用可能な口座と投資信託商品は次のとおりです。
- 特定
- 一般
- 積立NISA
- 一般NISA
- 投信積立取扱銘柄
- 積立NISA取扱銘柄
積立NISAの上限である年40万円と、20万円分の積立投信を楽天カードから購入すれば、年間6000ポイントをゲットできますよ。

楽天ポイントを使って投資ができる
楽天ポイントを使って投資商品の購入(ポイント投資)ができます。
- 投資信託
- 国内株式
- バイナリーオプション
このうち投資信託の購入はSPU(楽天スーパーポイントアッププログラム)が適用され、楽天市場のポイント獲得が+1倍になります。
SPUの適用条件は
- 投資信託のポイント投資
- 購入額500円以上
- 楽天ポイントコースに設定
の3つです。
ポイント投資詳細は楽天証券HPで詳しく説明されています。
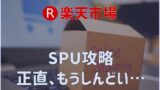
ポイント投資できる額は会員ランクによって上限が変わりますが、ダイヤモンド会員以外で1カ月10万ポイントが上限なので不自由はなさそうですね。
本来なら利息の付かないポイントが、投資によって複利で増えていくのはかなりのメリットです。有効活用して資産形成スピードをアップしたいところですね。

楽天ポイントがためやすい
楽天銀行とマネーブリッジで連携し、ハッピープログラムを有効化することで楽天ポイントがためやすくなります。
- らくらく入金
- 自動入金(スイープ)
- 楽天証券での取引
でポイントを獲得できます。
またハッピープログラムを有効化し、かつ50万円以上の投資信託を保有していると、資産額に応じて毎月ポイントがもらえます。
楽天証券で投資信託を購入する場合は楽天銀行との連携サービスマネーブリッジと、ハッピープログラムの有効化を忘れずにおこなうようにしましょうね。
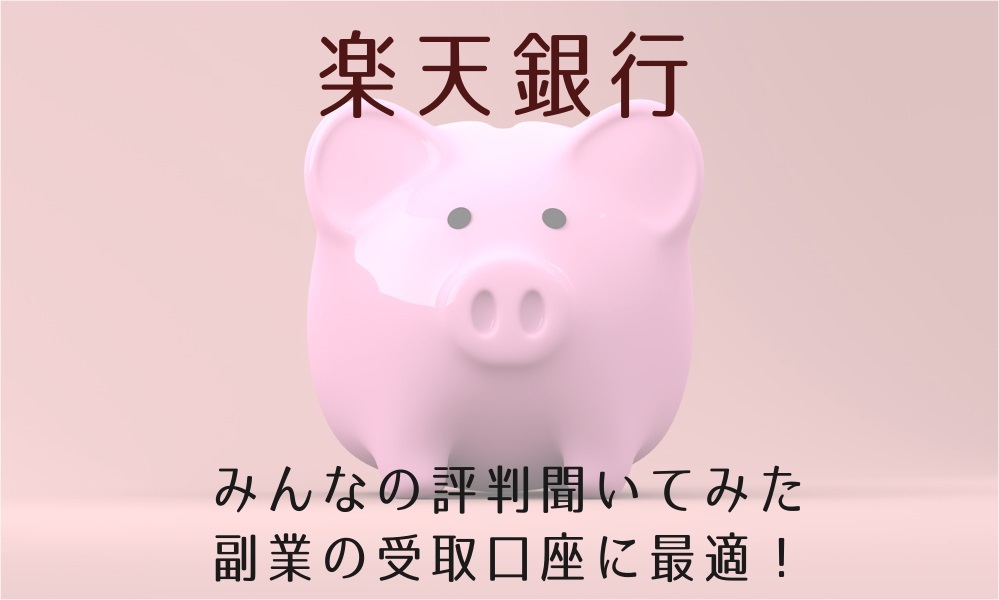

日経テレコン(楽天証券版)が無料で読める
日本経済新聞社が提供するビジネスデータベースサービス【日経テレコン】が無料で利用できます。
提供されるサービスは
- 日本経済新聞(朝刊・夕刊)、日経産業新聞、日経MJなどの閲覧(3日分)
- 過去一年分の新聞記事検索
- 日経速報ニュースの閲覧
日経テレコンはまともに契約したら月額6000円〜かかるので、機能に制限があるとはいえ無料で利用できるのは大きなメリットです。
SBI証券を使うメリット。手数料・IPO・総合力で強い!

SBI証券のメリット、強み部分について解説します。
投資信託の積立に三井住友カードが使える
楽天証券と同じくクレジットカード決済で投資信託購入ができます。
利用可能なクレジットカードは三井住友カード(独自ポイントがたまるカード以外)
ポイント還元率は0.5%、上限は1カ月5万円。
獲得できるポイントは三井住友カードのVポイントです。
Vポイントは楽天ポイントのように投資商品の購入はできませんが、ANAマイレージへの交換や、さまざまな商品購入に利用できる汎用性の高いポイントですよ。
クレジット決済が利用可能な口座と投資信託商品は次のとおりです。
- 特定
- 一般
- 積立NISA
- 一般NISA
- 投信積立取扱銘柄すべて
IPO銘柄に強い
SBI証券はIPOの取扱件数が多い特徴があります。
過去の取扱件数実績もダントツで、2020年には85件の取扱実績がありました。
2020年の新規上場数が102なので、80%以上を取り扱ったことになります。
投資初心者でIPO投資をすることはないと思うので、「そんなメリットもあるんだ」程度で思っておけばいいと思います。
9カ国の外国株に投資ができる
外国株の取扱国、取扱数ともネット証券の中で最多クラスです。
- 米国株 約3500銘柄
- 中国株 約1400銘柄
- 韓国株 約60銘柄
- ロシア株 約30銘柄
- ベトナム株 約320銘柄
- インドネシア株 約70銘柄
- シンガポール株 約40銘柄
- タイ株 約70銘柄
- マレーシア株 約40銘柄
米国株以外にどれだけ投資する人がいるかはわかりませんが、選択肢が多いことはいいことですからね。


米国株購入時の為替手数料が安い
SBI証券の最大のメリットと私が考えているのが、米国株購入時の為替手数料を安くおさえられることです。
通常米国株を購入する際には日本円をドルに交換(ドル転)する必要があります。
この時の為替手数料が4銭/ドルと格安です。
ただし普通にSBI証券でドル転すると25銭/ドルかかってしまいます。
住信SBIネット銀行でドル転した時のみ4銭/ドルで交換できるので、住信SBIネット銀行でドル転して、SBI証券に入金することで格安にできるわけです。
その際の入金手数料は無料です。
iDeCo対象銘柄が優れている
SBI証券iDeCoは「セレクトプラン」を選択すると対象銘柄にeMAXIS Slimシリーズが選べます。
米国のS&P500に連動したインデックスファンド等に低コストで運用できる人気商品です。
楽天証券にも超優良ファンドの楽天VTIを選択できますが、コスト面でeMAXIS Slimの方が勝っていますね。

楽天証券とSBI証券の比較一覧

楽天証券とSBI証券の取引スペックを比較していきます。
国内株式
楽天証券、SBI証券とも国内株式の取引手数料には2種類の料金体系があります。
- 一日の取引合計額で手数料が決まる
-
楽天証券:いににち定額コース
SBI証券:アクティブプラン - 一回の取引金額で手数料が決まる
-
楽天証券:超割コース
SBI証券:スタンダードプラン
| 一日の約定代金合計 | 楽天証券 (いちにち定額コース) |
SBI証券 (アクティブプラン) |
|---|---|---|
| 100万円まで | 0円 | 0円 |
| 200万円まで | 2200円 | 1278円 |
| 300万円まで | 3300円 | 1718円 |
| 以降100万円ごと | 1100追加 | 440円追加 |
| 約定代金 | 楽天証券 (超割コース) |
SBI証券 (スタンダードプラン) |
|---|---|---|
| 5万円まで | 55円 | 55円 |
| 10万円まで | 99円 | 99円 |
| 20万円まで | 115円 | 115円 |
| 50万円まで | 275円 | 275円 |
| 100万円まで | 535円 | 535円 |
| 150万円まで | 640円 | 640円 |
| 3000万円まで | 1013円 | 1013円 |
| 3000万円以上 | 1070円 | 1070円 |
デイトレーダーでもない限り一日の約定代金が100万円を超える人はそうそういないと思うので、実質両社とも手数料は0円と考えていいでしょう。
楽天証券の超割コース、SBI証券のスタンダードプランは、手数料の一部がポイントとして還元されます。
- 楽天証券:1.0%(楽天ポイント)
- SBI証券:1.1.%(SBIポイント)
外国株式・海外ETF
外国株式・海外ETFでは各社で差がでてきます。
株式を購入できる国
前述したとおり、SBI証券は世界9カ国の株式に投資できるのが特徴です。
| 取扱国株式 | 楽天証券 | SBI証券 |
|---|---|---|
| 米国株 | 約2960銘柄 | 約3500銘柄 |
| 中国株 | 約920銘柄 | 約1400銘柄 |
| 韓国株 | − | 約60銘柄 |
| ロシア株 | − | 約30銘柄 |
| ベトナム株 | − | 約320銘柄 |
| インドネシア株 | 約72銘柄 | 約70銘柄 |
| シンガポール株 | 約49銘柄 | 約40銘柄 |
| タイ株 | 約74銘柄 | 約70銘柄 |
| マレーシア株 | 約43銘柄 | 約40銘柄 |
| 海外ETF | 約365銘柄 | 約340銘柄 |
為替手数料
各国通貨へ交換時の為替手数料の比較です。
| 海外通貨(/日本円) | 楽天証券 | SBI証券 |
|---|---|---|
| 米ドル | 25銭 | 25銭 |
| ユーロ | 50銭 | 80銭 |
| 英ポンド | 70銭 | − |
| 豪ドル | 70銭 | 100銭 |
| NZドル | 70銭 | 100銭 |
| カナダドル | 80銭 | 80銭 |
| 南アランド | 30銭 | 30銭 |
| 香港ドル | 香港株15銭 上海株20銭 |
15銭 |
| 韓国ウォン | − | 20銭(100ウォンあたり) |
| ロシアルーブル | 8銭 | 8銭 |
| ベトナムドン | − | 200銭(10000ドンあたり) |
| インドネシアルピア | 3銭 | 3銭(100ルピアあたり) |
| シンガポールドル | 83銭 | 83銭 |
| タイバーツ | 8銭 | 8銭 |
| マレーシアリンギット | 43銭 | 43銭 |
両社ほぼ横並び状態ですが、SBI証券は同グループの住信SBIネット銀行で交換してから証券口座に入金する方法がもっとも為替手数料を安くすることができます。
その際の為替手数料は次のようになります。
| 通貨(/日本円) | 楽天証券 | 住信SBIネット銀行 |
|---|---|---|
| 米ドル | 25銭 | 4銭 |
| ユーロ | 50銭 | 13銭 |
| 英ポンド | 70銭 | 28銭 |
| 豪ドル | 70銭 | 25銭 |
| NZドル | 70銭 | 25銭 |
| カナダドル | 80銭 | 25銭 |
| 南アランド | 30銭 | 14銭 |
| 香港ドル | 香港株15銭 上海株20銭 |
5銭 |
どうでしょう?
購入手数料が横並びなので、金額が多くなるほど為替手数料の差が大きく効いてきます。
【例えば】
米国株購入を想定した場合の為替手数料で見てみると
100ドル分購入
楽天証券:25円
SBI証券:4円
10000ドル分購入
楽天証券:2500円
SBI証券:400円
為替手数料は行き帰りの両方で発生するので、最終的に日本円に戻した時は倍です。
取引手数料
株式の買い付け時に発生する手数料です。
米国株式
| 楽天証券 | SBI証券 | |
|---|---|---|
| 取引手数料 | 約定代金の0.495%(税込) | 約定代金の0.495%(税込) |
| 最低手数料 | 0ドル (2.22ドル以下) |
0ドル (2.22ドル以下) |
| 上限手数料 | 22ドル(税込) (4444.45ドル以上) |
22ドル(税込み) |
楽天証券、SBI証券両社とも米国株の手数料は横並びです。
中国株式
| 楽天証券 | SBI証券 | |
|---|---|---|
| 取引手数料 | 約定代金の0.55%(税込) | 約定代金の0.286%(税込) |
| 最低手数料 | 550円(税込) | 51.7香港ドル(税込) |
| 上限手数料 | 5500円(税込) | 517香港ドル(税込) |
投資信託
投資信託に必要なコストは主に3つです。
- 販売手数料:購入時にかかる費用
- 信託報酬:保有中にかかる費用
- 信託財産保有額:売却時にかかる費用
投資信託商品によって変わってきますが、楽天証券、SBI証券で大きな差はありません。
注意すべき点は、コストの高い商品を選ばないこと。最近は販売手数料無料(ノーロード)が基本です。
信託報酬も楽天VTIや、eMAXIS Slimシリーズなど優良ファンドであれば0.1〜0.2%程度までおさえられます。
中には信託報酬が2%を超えるようなファンドもあるので注意が必要ですね。
1000万円を運用した場合の年間コストが20万円です。10年投資したら200万円。
これでは上手に資産形成なんてできませんからね。
投資信託で両社間に違いがでるのは積立頻度とポイント還元です。
| 楽天証券 | SBI証券 | |
|---|---|---|
| 自動積立最低金額 | 100円 | 100円 |
| 自動積立可能頻度 | 毎月 | 毎日 毎週 毎月 |
| 購入時ポイント利用 | ○(楽天ポイント) | ○(Tポイント) |
| 購入時ポイント還元率 | 楽天ポイント1.0% (楽天カード決済) |
Vポイント0.5% (三井住友カード決済) |
| 保有時ポイント還元率 | 0.048% (10万円ごとに4ポイント/月) 楽天ポイント |
通常銘柄:0.1%(1000万円未満) 0.2%(1000万円以上) 指定銘柄:〜0.05% Tポイント |
楽天証券の保有時ポイント還元率はハッピープログラム、マネーブリッジを有効化した場合の適用値になります。
iDeCo
手数料
| 楽天証券 | SBI証券 | |
|---|---|---|
| 加入時・移管時手数料 | 2829円 | 2829円 |
| 口座維持手数料 | 171円/月 | 171円/月 |
| 給付手数料 | 440円/回 | 440円/回 |
| 還付手数料 | 1488円 | 2148円 |
手数料面での差がほとんどありません。
取扱商品・信託報酬
取扱商品のライナップには差があります。
SBI証券のセレクトプランにはeMAXIS Slimシリーズがラインナップされるのが魅力です。
楽天証券の楽天VT、楽天VTIも十分に魅力的な商品ですが、コスト面でSBI証券が一歩上回っています。
| 楽天証券 | SBI証券(セレクトプラン) | |
|---|---|---|
| 米国株式 | 楽天VTI 0.162% |
eMAXIS Slim 米国株式 0.0968% |
| 全世界株式 | 楽天VT 0.212% |
eMAXIS Slim 全世界株式 0.1143% |
| 先進国株式 | たわらノーロード先進国株式 0.10989% |
eMAXIS Slim 先進国株式 0.10615% |
| 新興国株式 | インデックスファンド海外新興国株式 0.374% |
eMAXIS Slim 新興国株式 0.2079% |
【実例】楽天証券とSBI証券の使い分け方

ここまで楽天証券とSBI証券の強み部分を比較してきました。
その上で「どうやって使い分けるのが効率的に資産形成できるのか?」を私の実例をもとに解説しますね。
楽天証券の使い分け方
楽天証券のメリットをもう一度おさらいします。
- 投資信託の積立に楽天カード決済を利用できる
- 楽天ポイントを使って投資ができる
- 楽天ポイントをためやすい
- 日経テレコン(楽天証券版)が無料で読める
楽天証券のメリットは何と言っても楽天ポイントのためやすさにあります。
私は次のような使い方をしていますよ。
- 楽天カード決済で積立NISAでコツコツ積立投信
- 楽天カード決済で投資信託を積立
これが私の使い方です。
その他にも楽天経済圏で積極的にポイントをためているようなも楽天証券のメリットを活かせると思います。
- 楽天カードを持っている
- 楽天経済圏でポイントをためている
- 楽天市場での物品購入がメイン
SBI証券の使い分け方
同じくSBI証券のメリットについてもおさらいします。
- 投資信託の積立に三井住友カードが使える
- IPO銘柄に強い
- 9カ国の外国銘柄に投資ができる
- 米国株式やETFをメインに投資
- iDeCo対象銘柄が優れている
SBI証券は住信SBIネット銀行との連携によるドル転時の手数料4銭/ドルが一番のメリットです。
SBI証券なら次のような使い方ですね。ちなみに私はiDeCoには使ってません。
- 成長性の高い米グロース株や、米高配当株等への投資を低コストで行う
- iDeCoをeMAXIS Slimシリーズメインで積立投資する
まとめ:楽天証券とSBI証券を使い分けて上手に資産形成しよう

いかがでしたか?
この記事では楽天証券、SBI証券の二社を使いこなすために三つのポイントで解説をしてきました。
- 証券口座を分けることのメリット
- 楽天証券・SBI証券のメリット
- 証券口座の使い分け方実例
ネット証券は各社特色があって選び方がむずかしいですが、一社に絞るより各社の強みを活かして使い分けるのがおすすめです。
楽天証券とSBI証券はネット証券の最大手。
今後も競い合って私達投資家にうれしい商品をどんどん展開してくれると思います。
二つの証券口座を上手に使って効率よく資産形成していきましょう!
この記事があなたの役にたつようであればうれしく思います。


